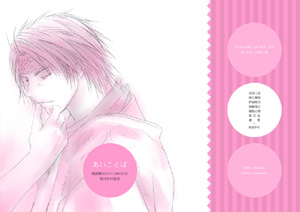
これは親しくしている他の者に聞いても納得する人物だろう。彼らも同じように尊敬する人物と言われれば、己の主の名を挙げるに決まっている。
兼続は、ここのところずっと不思議に心が温かかった。何故だかはわからない。だが、謙信がこの世を去って以来、久しぶりの安息を得たような感覚の中にいる。
何故だろうか、とその大元を辿るように、自分に向き合うことが増えた。
任されている上杉の政務は多い。ぼんやりしている暇はあまりないのだが、それでも気がつくとぼんやりしてしまっているのだから仕方がない。その時も、ぼんやりして筆を硯の上でのたくたと動かしているだけだった。
「どうしたい、兼続」
「手の上なら尊敬のキス」
正則にとっては「女にもてる」というのは一大事である。
小さな頃から、秀吉とねねの仲睦まじい夫婦を見ているのだ。伴侶というのが大切な存在である事はつくづくよくわかっている。だからこそどうにかしたいものだが、残念ながら今のところ縁はない。焦らずともいつか必ずそういう人が現れるよ、とねねなどは言うが、健全な男性であれば女にもてたいという気持ちがあって当然で。
ならばと周囲を見てみるが、清正も三成も、あまり女性とは縁がない気がした。そもそも理想の女性像といえば、ねねと答える清正と、そしてそんなことをいちいち聞いてくれるなとあしらってくる三成である。二人の周囲もどちらかというと男くさいし、かといって周囲にいつも女性がいるような宗茂には死んでも聞きたくない話である。
「なーっとくいかねぇ!」
「額の上なら友情のキス」
左近にとって、緻密な策は必ずどこかで予定外のことが起こるものだ。
その綻びが、策の全てに影響を及ぼしていく。残念ながらそこをうまく抜け出す策は、若い頃の左近には思いつかなかった。その為に、武田信玄へ軍略を学ぶ為に訪れたのだ。
「なるほどなるほど。それで左近は、その綻びをどう修復するのか。それを学びたいわけじゃな」
酒を酌み交わしながら軍略について語ることも増えていた。大概信玄は最初は酒がまずくなるのぅと渋るが、気にせず話をしていれば信玄はおのずとのってくる。
「左近は幸村、どう思うかね?」
「頬の上なら満足感のキス」
三成が幸村に、想いの丈をぶつけたのは少し前の事になる。
幸村から返事をもらったのがそれから数日後。
三成はついに幸村を手に入れることになったのだった。
そして、それまでは思いもよらなかった事に対して三成は酷く難しく悩んでいた。
それまでも気にする部分はあったのだ。人より細いところ、肌の白いところ、体力に関しても。
三成は、目鼻立ちの整った顔をしている。左近に言わせれば綺麗な顔だが人形めいているという。それが長所でもあり短所だとも。
顔の事もあるが、一番気になるのはその体格だ。
「唇の上なら愛情のキス」
「やる」
ぽつり。
呟いた言葉を聞き咎めたのは、あの戦の最中、拾った雑賀孫市だけだった。彼が、「え?」と目だけで問うてくるのを、威圧するように睨んだ。誰の反発も受け付けるつもりはなかった。政宗の心はもう決まっていた。
「戦はまだ終わっておらぬ」
その言葉の奥底には、熱がこもっていた。この熱に浮かされているうちに動かなければいけない。この熱が、あの雨で勢いを消すのをただ待つわけにはいかない。
時は慶長十九年。
大阪夏の陣が終わり、今まさに徳川家康が天下人として世の中にその姿を知らしめた。その瞬間だった。
「閉じた目の上なら憧憬のキス」
清正は存外に面倒見がいい。宗茂が誾千代と喧嘩したとなれば一応避難場所の提供もしてやっていた。正則が前を見ないのに対して、毎回ぎりぎりで最低限の忠告をしてきた。秀吉とねねがいた頃は、二人が秀吉の浮気癖で喧嘩するたびにねねの泣きごとをずっと聞き続けたし、秀吉との間も何度も取り持ってきた。三成も三成で、仲は悪かったがそれなりにうまくやっていた。
たぶんそういう星のもとに生まれてきているのだ。
つくづくそう思っていたところで、今回の幸村である。
「おい、どうだ」
「掌の上なら懇願のキス」
たくさんの、名前が出る。
趙雲は幸村と話しながら、次第に膨れ上がってくる感情にいつも首を傾げていた。幸村との会話は楽しい。だがそうして会話をした後、よく胸が焼けるような錯覚に苦しんだ。
思わず胸をかきむしって、その痛みごとなくしてしまいたくなるような。
趙雲は強い。この遠呂智の世界に来て、はじめてどうしようもないほどの敗北を体験したものの、普段の強さは関羽や張飛といった人物たちと肩を並べるほどだった。
戦場に出ることも多い身だ。戦で負う傷の痛みには、差はあれど慣れている。だが今回のこの痛みは到底慣れられる気はしなかった。
どうすればいいかわからず、その日ついに趙雲は、相談をしてみる事にした。
――幸村本人に。
「腕と首なら欲望のキス」